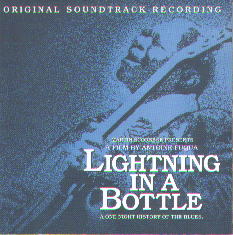
レコード・ジャングル 中村政利
ブルース生誕101年だそうである。アメリカ合州国議会が2003年をブルース生誕100周年と決め、さまざまなセレブレイション行事の実施を決議した。遅れて今年そのフィーバーが日本に上陸し、レコード会社、映画会社、出版社、放送局、大手レコード店を巻き込んでのキャンペーンが張られた一年となったというわけである。いったい何を基点として101年が数えられているのかは知らないが一世紀というのはかなり短い。50歳を間近に迎えたボクでも「やっとそんなもんか」という感慨を持ってしまう。ボクがブルースを聴き始めて33年。ということは、ブルースの歴史の三分の一とリアルタイムに付き合ってきたことを意味する。だが自分がブルースと付き合いだしたころにはすでにブルースは過去の音楽になろうとしていたし、一部の例外を除いて、50年代のスリル感を凌駕するリアルタイムのブルースとはめったに出会うこともなかった。だから、自分が聞き始めた時点ですでに「過去から学ぶ音楽」であった。
最初の出会いはおそらくテレビ番組であったろう。NHKが「ヤング・ミュージック・ショー」と名付けて不定期に海外の音楽フィルムを放送していたことがあった。タイトルは忘れたけど、ロンドン郊外の工場跡のような大きな建物の中で1969年に撮影されたエリック・クラプトンやジミー・ペイジをはじめとするブリティッシュ・ロックのスターたちによるスーパー・セッションにいきなり現れ、火を噴くような緊張感あふれるギターを弾いていたバディ・ガイの印象は中学生のボクにはあまりに毒が強すぎた。
音楽に何を求めるかは人によってさまざまだろう。癒しであったり、和みであったり、開放感であったり、励ましであったり、それは音を楽しむという裏づけさえあればなんでも構わないことだ。ただボクには「激しさ」という感覚が、自分が音楽に対峙するもっとも重要なキーワードであり続けてきた気がする。
中学で洋楽に目覚めたボクにとって初めて出会った激しい音楽はビートルズとその仲間のロックだった。高校生になるとモダン・ジャズやフリー・ジャズの楽器の生音にリアリティーを感じるようになる。東京の大学生となって、図書館でレコードを借りることをおぼえてからはめぼしいロックやジャズのLPはあらかた聴きつくしただろう。ジョン・コルトレーンの来日ライブの3枚組を返しに行った時、自身がジャズ・ファンらしき図書館員が「これ最後まで聴けましたか」と訊ねてきた。どうやらかれにとっても大多数の借り手にとっても、ジャズとは「教養として聴くもの」だったらしい。
小石川図書館で借りるものがなくなり、渉猟の場を同じ文京区の真砂図書館に移した時、開架式のレコード棚の一角を占めるブルースのLPコレクションが目にとまった。引き寄せられるように手にしたエルモア・ジェームズのソニー/アリスタ盤。白地にエルモアの坊主頭の白黒写真が無愛想にそびえるようなジャケット。そのそっけなさが新鮮だった。レコードの存在そのものに重みがあった。
わくわくしながら針をおとした最初の音に腰が抜けた。まさに探していたものがそこにあった。どんなハードロックよりも鋭いリズム。どんなフリージャズよりも暴力的なサウンド。そしてどんな演歌よりも張り詰めた歌。積年、自分が求め続けてきて満たされることの無かった「激しさ」のすべてがそこにあったのだ。それも外見では無く内面からにじみ出る激しさとして。
すぐにデパートで安いユナイト盤でエルモアのLPを2枚買い、ほとんど一ヶ月そればかりを聴き狂った。そのうちブルースの話法に慣れてくると、それぞれに別の肌触りで「秘めた激しさ」を持つ図書館の200枚ほどのLPがすべて宝物のように思えてきた。
目の前でうつむいていた得体の知れない老人のような「ブルース」の腕が有無を言わさず伸びてきて、口から、のどからダイレクトに身体の中に入り込み、心臓ごと魂をわしづかみにしてしまい、自分ではけっして振りほどくことができない。それがブルースを知るということ。そして、その状態はいまも続いている。
ブルース101年。そしてボクのブルース歴30年。あらためて思うのは、いったん身に付いたその美学は、時代が移ろうとも、自分自身が如何に変わろうとも、微塵の変化もないということ。極端を承知で、さらに言えば、音楽のみならず、文学、美術などの芸術作品、いや、社会を見る目そのものがブルースを知る前と知った後とではあきらかに違う。あたかも、この世に、ブルースを知る知らないで二通りの人間がいるかのように。
さきに「過去から学ぶ」と書いたが、音楽はけっして頭で教養として学ぶものではない。それは、出会うものであり、体験するものだ。多くのすぐれたブルースのように、たとえ過去の音楽であっても、こんにちの自分にとって切実な体験を与えるものはある。そしてブルースで知った血をたぎらせるような音楽との出会いを求めてボクはいまでも音楽渉猟を続けているのだ。
今回はこの2004年一年間を振り返って、新たにボクの血をたぎらせた、ブルース・スピリットあふれる5枚のレコードを紹介しよう。
VA/Lightning In A Bottle (Columbia/Legacy C2K 92860) \2580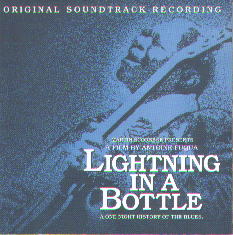
数多いブルース100周年記念アルバムのうち、もっともボクを感心させ、また感動させたのがこの2枚組みCDである。時は2003年2月7日、ところはニューヨークのラジオ・シティ・ミュージック・ホール。ブルースの歴史を一夜でたどる”Salute To The Blues”と題されたコンサートのライブ盤だ。
ここに集まったのは、戦前からデルタで活動していた第一世代のブルースマンである93歳のハニーボーイ・エドワーズを筆頭に40年代からこんにちまでブルースの顔として活躍してきた功労者たちと、60年代以降ロックやジャズのフィールドでその伝統を受け継ぎ発展させてきた、ナタリー・コールやジョン・フォガティーらのスターたち、そして、モス・デフ、チャックD、シェメキア・コープランドのように21世紀の「ブルース」を創造する新しい感覚の若手音楽家たちだ。
アルバム冒頭の曲がポール・オリバーの「ストーリー・オブ・ザ・ブルース」と同様にアフリカ人アンジェリック・キジョ(ベニン出身)の演奏で始まり、デルタ・ブルースからシティ・ブルース、シカゴ・ブルース、R&B、ソウル、ヒップホップへという大きな流れのもとに、時代を画した代表的名曲が、一見意外だが考えればふさわしい人選で演奏されるという構成は見事だ。
ジャケットを広げるとポスターのように大きくなる、さまざまな分野でブルースへの敬意と愛情を忘れない60名を超える音楽家が勢ぞろいした記念写真も見飽きない。このコンサートも、ブルース・ムーヴィー・プロジェクトの7作品と同様にマーティン・スコセッシの指揮のもとで映画化されており劇場にかかるのが楽しみだ。ボクには番外編のこの作品が本編以上に魅力的に思われる。
Candi Staton/S.T. (Astralwerks
94432) \1200(特価)
非の打ち所の無い名盤があるとすれば、キャンディ・ステイトンのフェイム・レコードから出た最初の2枚のLPがそうだと信じているソウル・ファンは多い。それが全曲聴けてしまうのだ。シングル盤でしか聞けなかった4曲と、次のアルバムからの4曲も加えて。まさに一家に一枚の決定盤が誕生した。
だが、これが「ソウル」を代表する音楽かというとけっしてそうとは言い切れない。ソウルとカントリーとポップスの3要素がブレンドした絶妙なバランスの上に立ったきわめて独特で繊細な名盤であるからだ。単純に言えば、題材はカントリー・ナンバーが主だし、バックの演奏もアクの強さこそあれカントリー音楽のものだ。ストリングスやホーンやコーラスを配した親しみやすいアレンジはヒットポップス的な傾向が強く、それに乗っかるキャンディのうたいまわしはゴスペル直系のソウルそのもの。その声質がいい。決して豊かではなくハスキーでためらいがちで、たどたどしくさえ聞こえる。そこが、女の心の傷を表現するにはうってつけで、人生のはかなさともどかしさとあきらめとを切実に感じさせる。
それらが70年頃というソウルもカントリー音楽もティーン・ポップも煮詰まった絶妙の時期に、過不足無く混ざり合って化学変化を起こし、南部はアラバマのマスル・ショールズでプロデューサーであるリック・ホールのもろくも壊れやすい砂糖菓子のようなマジックは完成したのだ。
たどたどしさが健気に聞こえるという意味ではイギリスから出現した17歳の白人少女歌手ジョス・ストーンの歌うソウルも今年の収穫だった。もっともキャンディ・ステイトンのこのCDには、はるかに普遍的な美しさがあふれている。
Da Problemsolvas/Every Woman Deserves 2B
Satisfied (Over 25 Sound 6 34479 90262
8)\2580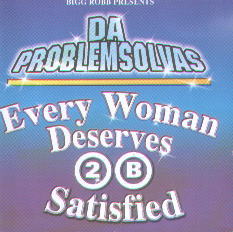
ジャズが器楽としての抽象性を志向するのとは逆に、ブルースは楽器すら肉体化して具象性を志向する。生々しく血の通った肉体性あふれる音楽を創り上げたという意味では、電子楽器を肉声の延長、あるいは音楽の肉体性を際立たせるもっとも重要な武器として活用した今は亡きロジャーは20世紀末を代表するブルースマンのひとりだったと思う。
そのロジャー率いるザップでサウンドの核となる電子楽器のアレンジをまかされていたビッグ・ロブが結成したのがこのプロブレムソルヴァーズである。音楽にしか能の無い3人らしく、ジャケだけ見ればけっして食指の動かない代物で、メンバーの写った裏ジャケットもまるで売れないヒップホップ・グループのようないでたちだが、そのサウンドは芳醇だ。誰が聞いてもザップの正当な後継バンドであることに異論は出ないだろう。いや、テクノロジーと肉体性の弁証法的な発展と融合という意味では青臭さのあったザップよりはるかに進化している。
このアルバムは、打ち込みの音なんてソウルやブルースには似合わないとのたまう石頭諸氏にこそ聞いてもらいたい。現代においてはテクノロジーを肉体化できるものだけが時代にあったリアル・ソウル・ミュージックを創り出せるのだということを証明する傑作アルバム。
ランキン・タクシー/Fallujah (Bacchanal 8115) \680
テクノロジーを肉体化するという意味では、北米黒人音楽よりもジャマイカのレゲエに一日の長があるかもしれない。そもそもジャマイカで発達したダブはレゲエ・シングルのB面のカラオケをDJたちが簡単なイコライザーを駆使してもっともメリハリの強い、暴力的な音を造ることを競い合うことで発達したものだし、さらには、それを伴奏にDJが自己宣伝やレコード販売の口上をまくしたてたのが北米に先行するラップの始まりなのだから。
今日では、ひとつのリズムトラックが作られれば、レコード会社がそれに乗せた歌手の歌やDJのラップの入った複数種類のシングル・レコードを同時発売するのが通例となっており、DJたちは、すでに出来上がったリズムトラックに時事性のたかいネタをほとんど即興芸の感覚でしゃべりこむ。そのことはソングスターとして事件やニュースを歌っていた初期のブルースマンとも共通する話法である。
CDアルバムには入っていないこの曲は日本人レゲエDJランキン・タクシーが日本語で、イラク戦争ファルージャでの米軍による虐殺行為を告発したドーナツ盤。もちろんジャマイカ以外では発売されておらず、しかも、トニー・カーティスの7インチ・シングルのB面でかろうじて発表されたもの。おそらく、当初はリズムトラックだけで出るはずだったB面にランキンがやむにやまれぬ思いからあわてて吹き込んだ曲に違いない。
決して、自分が脚光を浴びるはずの無いB面であっても、日本語でこの戦争の醜さをいま告発せずにはいられないというランキンの、正義感と、言葉のちからを再確認させる迫力ある節回し、ユーモアあふれる作詞能力におおいに感銘を受けた。
Los Lonely Boys/S.T.(Special
Edition) (EPIC/OR EK 93549) \2800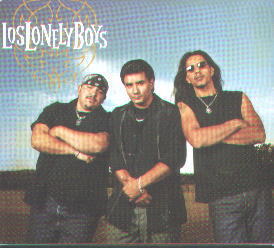
7月に5年ぶりに合州国を訪問したとき、サンフランシスコのモーテルのテレビでMTVで何度もかかるのを見て好きになったのがこのテックス・メックス・トリオだった。ヘンリー、ジョウジョウ、リンゴのガルザ3兄弟からなるグループでテキサスや西海岸での人気は絶大だ。
かれらの本拠地オースティンでのライブをビデオで見たが、何千人というメキシコ系の人々があたかも自分たちの親戚を応援するように老いも若きも一緒になって声援を送っていた。一般のロックがジェネレイション(世代)音楽であるのに対して、かれらは明らかにコミュニティー(地縁)やエスノロジー(民俗性)を支持基盤としているのだ。
かといって身内にコビを売るようなそぶりは少しもない。かれらの音楽は自然体で自分たちを育んだ風土を反映しているからだ。ハードロックもあれば、ラテンロックもあるし、メロウなバラードや、ルンバ・フラメンコ風のアコースティック曲もあり、どれもしっかりしたテクニックに裏打ちされ手堅い演奏でロス・ロンリー・ボーイズを主張する。
特筆すべきは、英語とスペイン語で唄われるボーカルの良さである。フレディー・フェンダーやデルバート・マクリントンなどのテックスメックス系シンガーに特有のセンチメンタルな歌心にあふれていて、どの曲も聞きほれてホロリときてしまう。
アルバムはこれ1枚だけなのに注文しても品切れで、ずっとヤキモキしていたら、DVDの付いたデラックス版で再発売となりようやく溜飲が下がった。